「関連記事を貼ってもクリックされない」
「ブログカードの配置がバラバラで統一感がない」
「導線は作ってるはずなのに、読者が止まってしまう」
それ、もしかして「“貼り方”じゃなく“見せ方”の問題」かもしれない。
この記事では、SilentGainが実践する
ブログカードと関連記事表示の“最適化戦略”を、
UX・視線誘導・回遊設計の観点から深掘り解説する。
◆ 1. なぜ関連記事やブログカードはクリックされないのか?
まず前提として、「関連記事」は貼っただけでは機能しない。
クリックされない主な理由は:
- 配置が不自然、文脈とつながっていない
- 見出しやデザインに視認性がない
- 表示場所と読者の“興味の流れ”が噛み合っていない
- 見出し(タイトル)が引きになっていない
- サイト全体でルール化されていないため、信頼性が育たない
つまり、関連記事の設置は「技術」ではなく「設計」で決まる。
◆ 2. 関連記事の配置位置を“感情の流れ”で決める
読者が“次を読みたい”と思う瞬間を狙う。それが最適な配置タイミング。
✅ 誘導しやすい3つのタイミング
| タイミング | 状態 | 関連記事例 |
|---|---|---|
| ① 強い共感・納得直後 | 読者が「なるほど…もっと知りたい」と思ったとき | 補足・深掘り記事へ |
| ② 読了後(まとめ後) | 読者の「次どうすればいい?」が発動 | 次ステップ・シリーズ記事 |
| ③ CTAの直前 | 収益記事やメルマガ誘導前に信頼強化 | 体験談・実績記事など |
タイミングを誤ると、読者は「押し付けられてる」と感じ、逆に離脱する。
◆ 3. 表示方法の選び方:UXと視線の流れを意識せよ
ブログカードや関連記事の表示には大きく分けて3タイプある。
✅(1)インラインリンク型(本文中リンク)
- テキスト内で自然に文脈とつながる
- 最もクリック率が高く、読者の流れを止めにくい
- “行動心理”に最も寄り添ったリンク方法
例:「この考え方をさらに深掘りしたのが、こちらの記事です。」
✅(2)ボックス型(カスタムブログカード)
- 視認性が高く、シリーズ感・特別感を出せる
- デザイン統一が信頼感に繋がる
- 目立ちすぎると読者が“広告”と誤解することもある
例:CanvaやSWELLなどでの「関連記事カード」表示(タイトル+画像+抜粋)
✅(3)自動表示型(ウィジェット・プラグイン)
- 手間いらずで関連記事を自動抽出
- 精度が低いと“関係ない記事”が表示されるリスク
- 放置型ブログでは「自動+一部手動」が理想
◆ 4. SilentGainの最適化ルールと設計思想
✅(1)シリーズ記事には「前回/次回」ナビ+ボックス誘導を統一
- 記事末にナビ+シリーズリンク集(アイキャッチ型)
- 同じ章構成で“読み進める快感”を演出
- 見た目の統一で「SilentGainらしさ」を体験してもらう
✅(2)収益記事への誘導は“信頼記事”をクッションに挟む
- 例:「収益化の武器」系記事の直前に「体験談」記事を配置
- 感情のグラデーションを作ることでコンバージョン率UP
✅(3)1記事に「最大2本」の“意図ある関連記事”を厳選
- 多すぎると読者が「どれを読めば…?」と迷って逆に離脱
- “次に何を読ませたいか”を明確にし、役割を持たせて選ぶ
◆ 5. SilentGainで使っている実際の配置パターン
| 配置位置 | 内容 | 形式 |
|---|---|---|
| 本文中 | 理解補助/深掘り | インラインリンク |
| まとめ直後 | 次ステップ/シリーズ案内 | ボックス型カード |
| サイドバー | カテゴリ誘導・シリーズ導線 | 自動ウィジェット or 手動リンク集 |
| CTA前 | 信頼補強 | 経験談/実績リンク(インライン or ボックス) |
◆ まとめ:ブログカードと関連記事は“信頼と動線”の要
🔻 関連記事は「読者が今読みたいもの」を提案する設計が命
🔻 設置の場所・タイミング・形式で、クリック率が大きく変わる
🔻 ブログカードは「静かに誘導する接客ツール」である
SilentGainでは、“静かな誘導”で読者をスムーズに回遊させ、
結果としてPVと収益を自然に増やす“仕組み”を作っている。
🔚 記事の締め:導線ナビゲーション
なぜ何もしなくても読まれ続けるのか?“仕組みの正体”を明かす。
検索者の「本当の目的」を掘り当てると、刺さる記事になる。
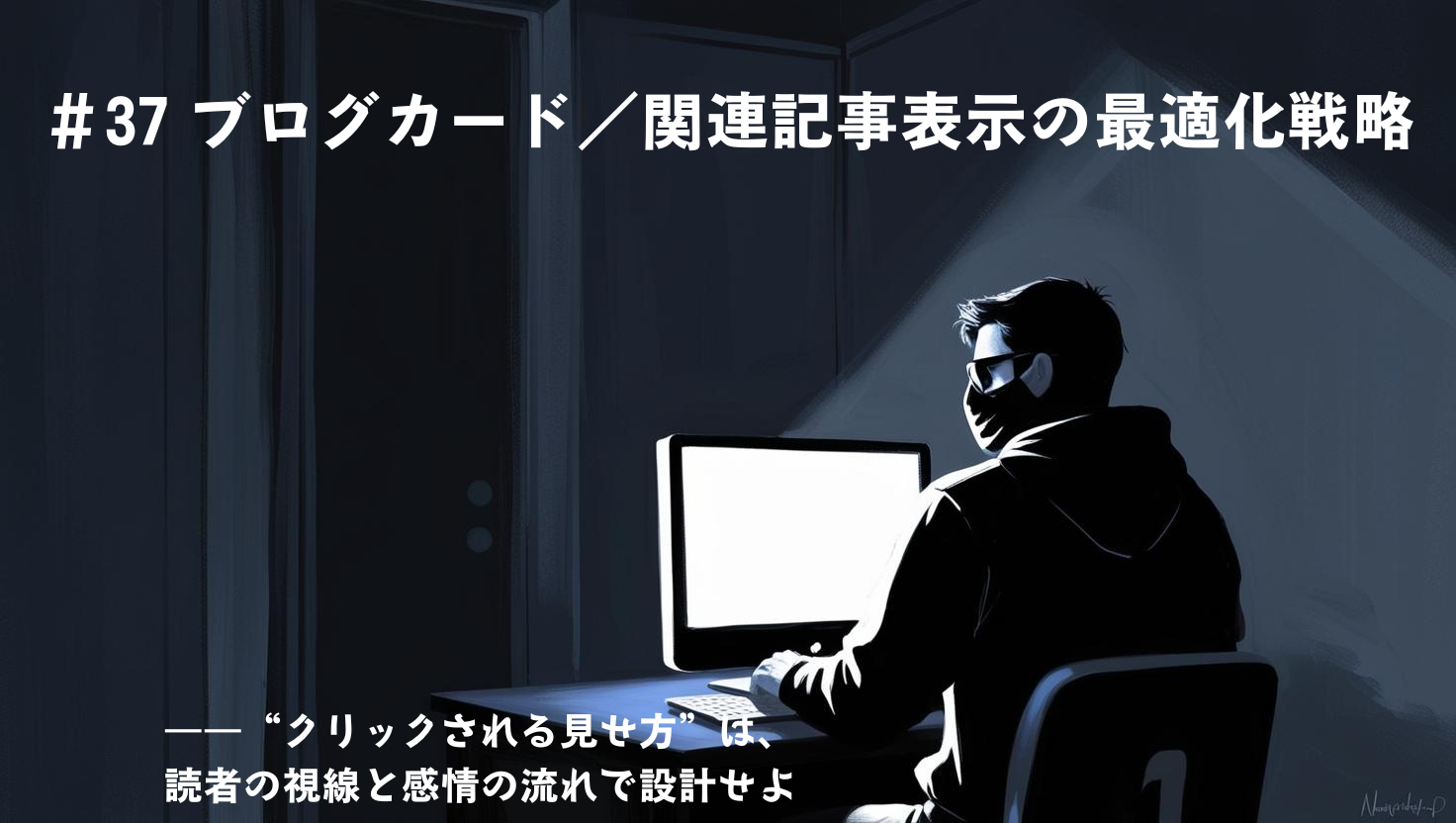

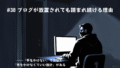
コメント